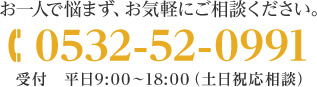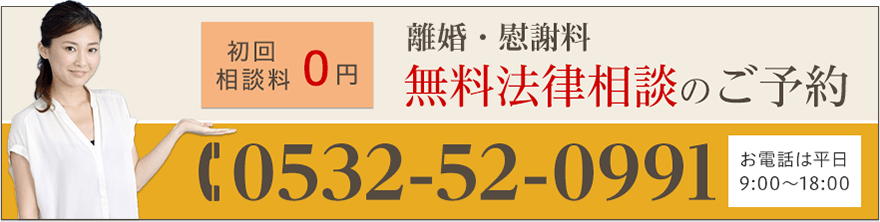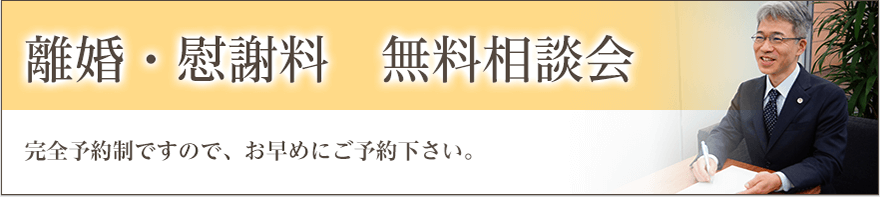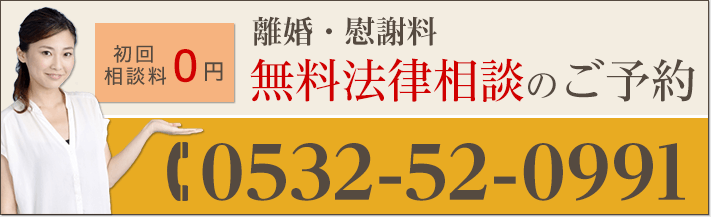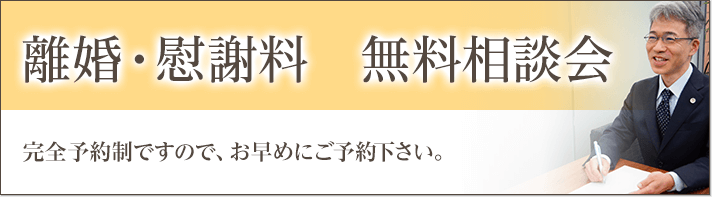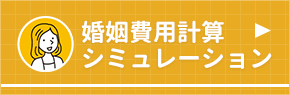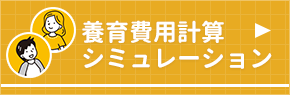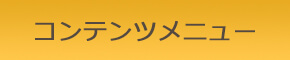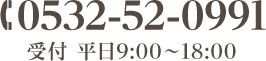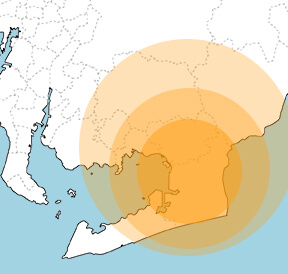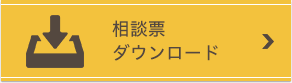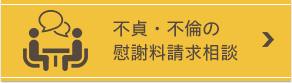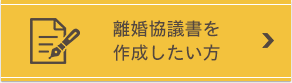【Q&A】財産分与と詐害行為取消権
質問
民法は、債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる旨規定しています。これを詐害行為取消権といいます。
それでは、多額の負債を負い、債務超過の状態にある者が、離婚時に配偶者に対して財産分与をしたときには、債権者は、詐害行為取消権を行使することができるのでしょうか。
弁護士からの回答
|
最高裁判所(最判昭和58年12月19日)は、離婚における財産分与は、「分与者が既に債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても、それが民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消の対象となりえないものと解するのが相当である」旨判示しました。 |
 |
したがって、財産分与が詐害行為取消権による取り消しの対象となるのは、上記のように限定された場合に限られると考えられます。
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?