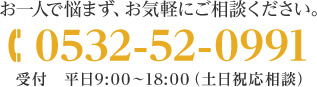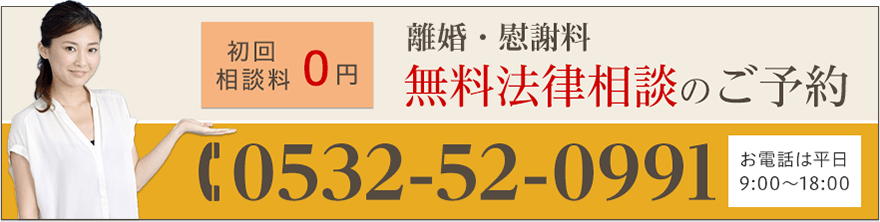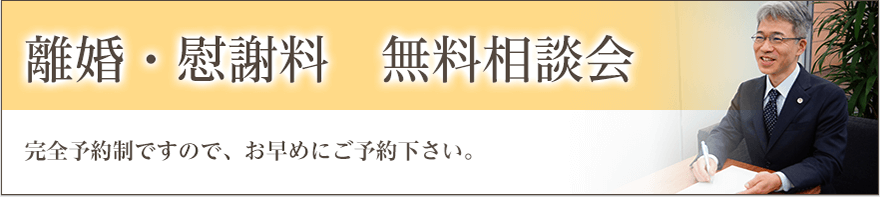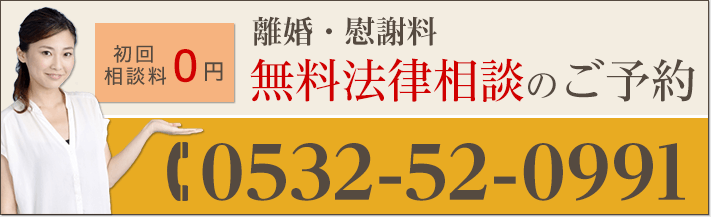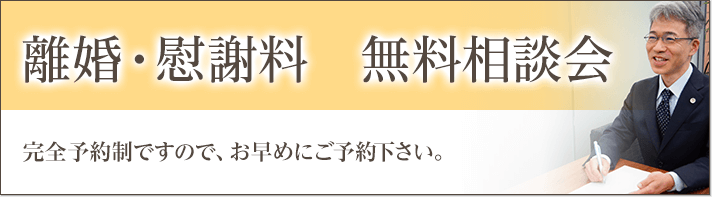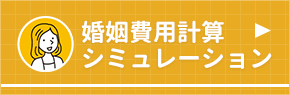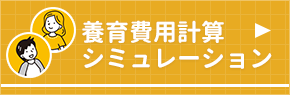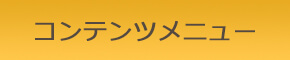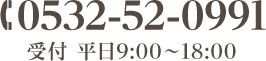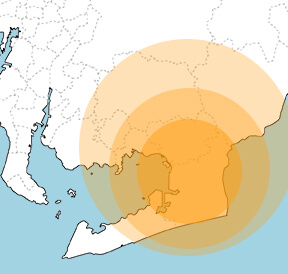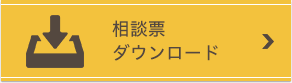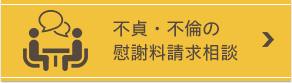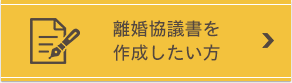スマホは離婚理由になる?最近多いスマホ離婚について弁護士が解説

1 はじめに
夫(妻)が家に帰るとスマートフォンばかり見ていて、一緒にいても楽しくない、会話がない、私のことに関心がないように感じる、といった場合、離婚をすることができるのでしょうか。
最近、スマートフォンの使い方などに端を発し、夫婦関係が悪化し、離婚に至り、「スマホ離婚」という言葉を聞くようになりました。
スマートフォンは、とても便利なものですが、一方、長時間、スマートフォンを使ってしまうことで、配偶者が不快な思いをする場合もあると思います。
スマホ離婚の原因になる行為とは
(1)スマートフォンばかり見ていて会話がない
家に帰ると、スマートフォンを見てばかりで、会話がない、家事や育児を手伝ってくれないという話を聞くことがあります。
スマートフォンを利用することで夫婦のコミュニケーションが減ってしまい、夫婦関係が悪化する場合もあると思います。
(2)スマートフォンを配偶者に勝手に見られてしまう
配偶者が浮気をしているか、チェックをするという意味で、配偶者のスマートフォンを勝手に見てしまった場合、見られた側としては、信頼されていないのではないかと感じたり、不快に思ったりする場合もあると思います。
スマートフォンを頻繁に見て、配偶者の行動をチェックしたり、監視していたりした場合、見られた側が不快に感じ、夫婦関係が悪化する場合もあると思います。
(3)スマートフォンのゲームの課金で家計を圧迫してしまう
スマートフォンのゲームをして、課金をしたとしても、それが本人の自由に使えるお小遣いの範囲内であれば、特段の問題にはならないことが多いと思われます。
もっとも、ゲームの課金が多額になり、家計を圧迫するようなことがあれば、夫婦関係の悪化につながる場合もあると思います。
(4)スマートフォンで浮気が発覚した
不貞行為の相手方とのSNSのやりとりや、不貞行為の相手方と一緒に写った写真をスマートフォンに保存していて、配偶者に見つかってしまった場合、不貞行為をした配偶者は、相手方から離婚を請求される場合があります。
一方、不貞行為をした側からの離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求となり、訴訟手続において、離婚請求を争われた場合、離婚が認められない場合があります。
配偶者に不貞行為があった場合は、配偶者が不貞行為をした場合として、別途取り上げます。
(5)スマートフォンを使って、オンラインでギャンブルをしている
インターネットを利用して、競馬、競艇等をすることができるようになっています。
スマートフォンを使って、競馬、競艇等をした場合には、配偶者がギャンブルをした場合として、ここでは、取り上げません。別途、ギャンブルと離婚というテーマで取り上げる予定です。
スマートフォンの使用が夫婦関係の悪化につながらないように、日頃から、夫婦で十分にコミュニケーションを取り、お互いに相手方を気遣いながら、節度を持って、スマートフォンを使うことが望ましいと個人的には思います。
なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。
2 離婚原因
民法は、離婚原因として、
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
を規定しています。
スマートフォンばかり見ているといった場合、婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当するか否かがポイントになります。
もっとも、単に同居中、スマートフォンを見てばかり見ていたというだけでは、一般論として、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるときには該当しないと思われます。
一方、スマートフォンの利用に端を発し、夫婦関係が悪化し、別居に至る場合もあると思います。
離婚を求める側は、夫婦関係の悪化の経緯等を詳細に主張し、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるときに該当すると主張することになると思います。
3 離婚の手続
離婚の手続は、どのように進んでいくのでしょうか。
(1)離婚協議
まず、当事者同士で、離婚の話し合い(協議)を行うことが多いと思います。
(2)離婚調停
離婚の協議がまとまらないときや離婚の協議ができないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることが多いと思います。
離婚調停の申立をすると、調停期日が指定されます。調停期日では、調停委員の先生に事情を説明したり、離婚に関する意向を伝えたりします。
離婚調停において、合意に達すると、離婚が成立し、調停調書を作成します。離婚の届出をする当事者の方は、調停調書をもとに、離婚の届出をします。
離婚調停について、弁護士を依頼すると、弁護士が申立書を作成し、裁判所に提出します。調停期日には、弁護士が同席し、主に法的な意見を述べます。主張書面や証拠を提出する必要がある場合には、弁護士が、ご依頼者の方と打ち合わせをしたうえで、主張書面を作成し、裁判所に提出します。
弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをしたうえで、必要な証拠を提出します。調停手続において、合意に達する場合には、弁護士は、調停条項について、説明したり、助言をします。
(3)離婚訴訟
離婚調停の手続で合意に達しない場合には、離婚を求める側は、離婚訴訟を提起することが多いと思います。
訴状を家庭裁判所に提出し、訴訟を提起します。
離婚訴訟を提起すると、第1回の期日が指定され、指定された日に期日が開催されます。離婚訴訟では、主張については、準備書面に記載して、裁判所に提出します。また、必要に応じて証拠を提出します。
訴訟の期日では、裁判官が、原告、被告双方が提出した書面を確認したり、次回期日に向けた準備について、説明をしたりします。訴訟の途中で、当事者が合意に達し、和解になる場合もあります。判決になる場合には、当事者の方の尋問が行われることが通常です。
判決言い渡し期日に判決が言い渡されます。判決の主文に不服がある場合には、法律が定めた期間内に控訴することができます。
弁護士に離婚訴訟を委任すると、弁護士が訴状を家庭裁判所に提出します。訴訟の期日は、原則として、弁護士のみの出席で足ります。ただし、尋問期日等、ご本人のご出席が必要な場合もあります。弁護士は、ご依頼者の方とあらかじめ打ち合わせをして、ご依頼者の方の主張を準備書面という書面にまとめたり、必要に応じて証拠を提出したりします。
弁護士は、ご依頼者の方とあらかじめリハーサルをしたうえで、尋問期日にのぞみます。弁護士は、判決を受け取った後、控訴するか否か、ご依頼者の方と打ち合わせをします。
4 まとめ
離婚について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。