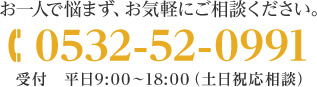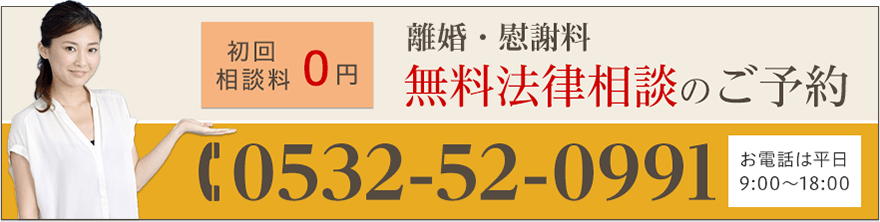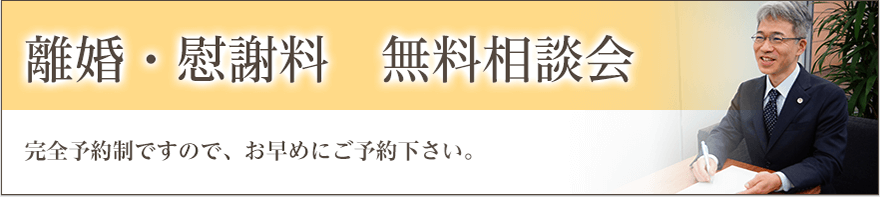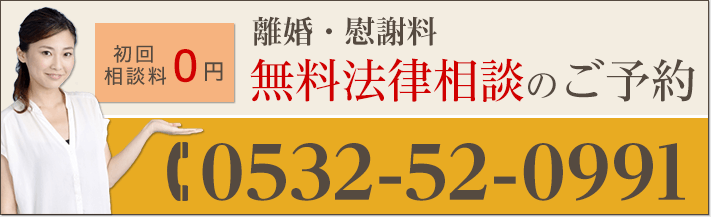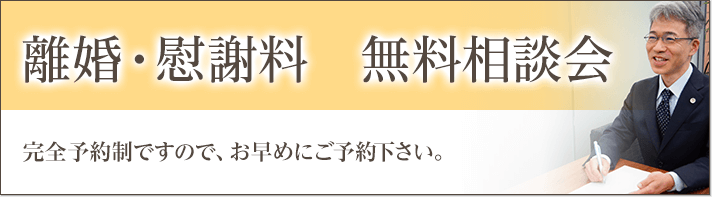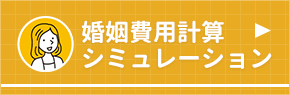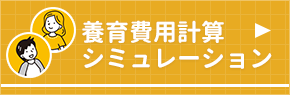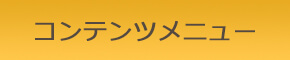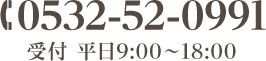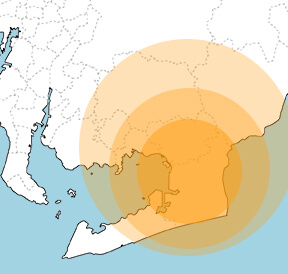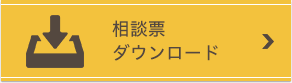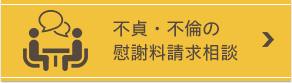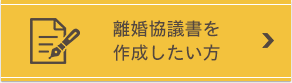コラム
【弁護士コラム】夫婦別姓
民法750条は、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する旨規定しています。これを夫婦同氏の原則といいます。 民法は、夫婦が別々の姓(氏)を名乗ることを認めておらず、婚姻届出の際に、夫婦のうち一方の姓を夫婦の姓として定める必要があります。 夫婦のうち一方は、結婚後に結婚前の姓を名乗ることができません。... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】再婚禁止期間
民法733条1項は、女は、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない旨規定しています。ただし、この規定は、女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から適用されません(民法733条2項)。 民法は、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しく... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】離婚、親権者の代理権濫用
養育費の合意成立後の請求手続 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代理します。 親権を行う者がその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。特別代理人を選任することなく、子を... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】摘出推定最高裁判
民法772条は、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する旨規定しています。 妻が婚姻中に懐胎した子であっても、常に夫の子とは限りません。 民法772条の推定を受けた子が嫡出であることを否認するためには、夫からの嫡出否認の訴えによらなければなりません(民法755条)。 また、嫡出否認の訴えは... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】教育費の増減額
離婚の際に当事者間で一度取り決めた養育費は、増減額する事はできないでしょうか。 養育費の支払いは、場合によっては、15年以上に及び、その間に父、母、子の状況が変化することはしばしばあります。 民法880条は、扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議... 続きはこちら≫
退職金は財産分与の対象になる?
退職金は、財産分与の対象になるのでしょうか。 退職金には、在職中の賃金の後払い的な性格があることから、財産分与の対象になるか、問題となります。 まず、結婚した後に勤務を始めた会社を退職し、退職金を受領し、その退職金が現存している場合、当該退職金は、原則として、財産分与の対象になると考えられま... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】財産分与
民法は、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる旨規定しています(民法768条1項)。 また、民法は、財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる旨規定しています(... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】嫡出推定最高裁弁論
民法は、 ①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する ②婚姻成立から200日を経過した後又は婚姻解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する 旨規定しています。 このように、妻が婚姻中に懐胎した子は、嫡出子と推定されます。 民法は、嫡出否認の訴えの... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】婚約の不当破棄と損害賠償
婚姻費用分担 婚約とは、将来結婚しようという当事者間の約束をいいます。 婚約の成立には、理論的には、必ずしも結納、指輪の交換、結婚式場の予約等は必要でなく、当事者間に将来結婚しようという真摯な合意があれば足りると考えられます。 しかし、実際に、婚約破棄に基づく損害賠償請求訴訟が提起され、婚約の有無が争点に... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】離婚の手続の種類
離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。 また、離婚訴訟においては、和解離婚、認諾離婚も認められています。 夫婦は、協議により、離婚をすることができます。具体的には、離婚届出書を作成して、市町村役場に提出すれば離婚が成立します。もっとも、夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚の届出に際し、... 続きはこちら≫