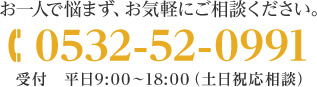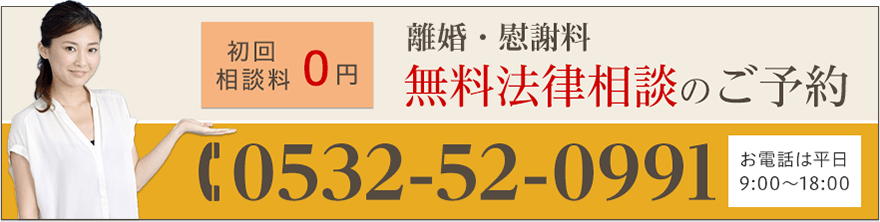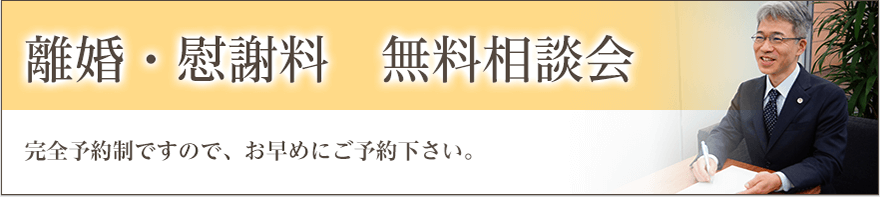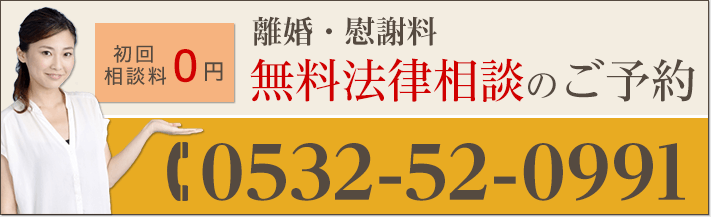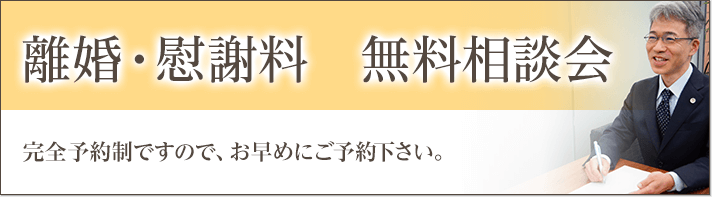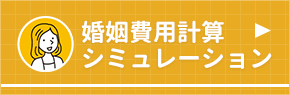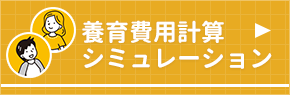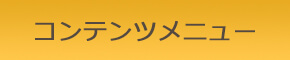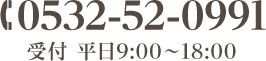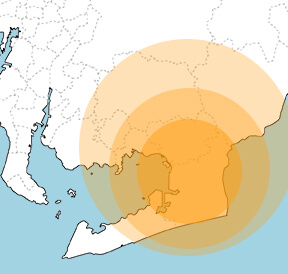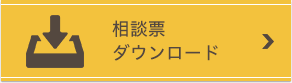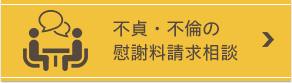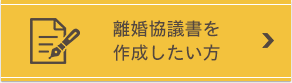年金分割について弁護士が解説
1 はじめに
年金分割は、夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。実際に分割されるのは、厚生年金の支給額の計算の基礎となる標準報酬の記録です。
年金分割の対象となる年金は、厚生年金、旧共済年金です。
国民年金は、年金分割の対象にはなりません。
年金分割には、合意分割と3号分割があります。
2 共働きでも年金分割を請求することができますか
共働きでも、年金分割を請求することができるのでしょうか?
共働きでも、通常、婚姻中、収入の少ない(標準報酬総額の少ない)方から、多い方へ、請求することができます。
その場合、通常、合意分割の方法をとることになると思います。
(1)共働きでも年金分割を請求できた事例
概要
私は、10年前に結婚をしました。私と夫の間には、3年前に生まれた長女がいます。
私の夫は、結婚前から、同じ会社で会社員として働いています。私は、結婚前から、会社員として働いており、出産の際は、産休、育休をとって、正社員として仕事を続けてきました。
私と夫は、昨年から、夫婦仲が悪くなり、離婚協議をしましたが、まとまらないので、離婚調停の申し立てをすることとなりました。私は、年金分割という制度があることを知りました。
私は、結婚前から、ずっと正社員として働いており、厚生年金に加入しています。
もっとも、婚姻期間中、私は、産休、育休をとっていましたので、その間、仕事を休職していました。
また、私の給与より、夫の給与のほうが高額です。
私と夫は、共働きですが、年金分割を請求することができますか。
結果
共働きの場合でも、年金分割を請求することができます。
もっとも、夫の厚生年金だけでなく、妻の厚生年金の標準報酬総額も含めて年金分割の按分割合を定めることとなります。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
3 年金分割の請求方法
(1)合意分割と3号分割
3号分割には、平成20年4月以降の第3号被保険者期間につき、第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。
3号分割は、合意分割とは異なり、相手方の合意等は、不要です。なお、3号分割としての年金分割の手続は必要ですので、注意が必要です。
また、3号分割は、平成20年4月以降の第3号被保険者期間を対象にしますので、平成20年4月より前の期間を年金分割の対象とする場合などには、合意分割の手続きをすることが必要になります。
一方で、合意分割では、当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めることが必要になります。
3号分割により分割される保険料納付記録は、平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られますので、注意が必要です。
(2)【Q&A】年金分割における3号分割制度と届け出
ご質問
私は、平成22年に夫と結婚しました。
私は、結婚前に既に退職していたため、結婚時には、無職でした。
私は、夫と結婚した後、ずっといわゆる専業主婦でした。夫は、結婚時から現在まで大企業で会社員として働いています。
私は、夫と離婚することとなり、年金分割という制度があることを知りました。私には、いわゆる3号分割という制度が適用され、3号分割では夫との合意は不要であると聞きました。
私は、夫と協議離婚をする予定ですが、市役所に離婚届け出を提出すれば、当然に婚姻期間中の厚生年金記録が分割されるのでしょうか。
弁護士の回答
| 3号分割の場合でも、離婚届け出を市役所に提出するだけでは、年金分割はされません。年金分割の手続きが必要であり、離婚後、法定の期間内に手続きをすることが必要になります。 年金分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |
(3)年金分割の方法
3号分割の場合には、通常、3号分割を請求する側が年金事務所に行き、単独で手続ができると考えられますので、ここでは、合意分割について、説明します。
夫婦が、話し合って、離婚の条件について合意し、離婚後に一緒に年金事務所まで出向いて手続をすることができれば、通常、問題は生じないと思われますが、以下、離婚調停、離婚訴訟、離婚後の年金分割の審判の手続について、説明します。
4 年金分割の割合とは
(1)年金分割の按分割合とは
按分割合とは、当事者双方の対象期間標準報酬総額を合計した額のうち、年金分割後における年金分割を受ける側の持分を示したものです。
例えば、対象期間標準報酬総額が、年金分割前において、夫が1億円、妻が2000万円である場合、按分割合を0.5と定めると、年金分割後の対象期間標準報酬総額は、夫と妻が同額(各6000万円)になると考えられます。
離婚調停において、ほとんどの場合は、按分割合が0.5と定められます。
また、離婚訴訟、において、判決となった場合、按分割合が0.5と定められることが通常です。
年金分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
(2)年金分割の案分割合を0、5(50パーセント)以外にすることはできますか?
| 実務上は、非常に困難です。離婚の調停、訴訟の実務では、ほとんど0、5(50パーセント)で分割しており、それ以外の割合での分割は、非常に困難です。 |
5 年金分割された年金の受給開始時期に関する事例
概要
私は、30年ほど前に夫と結婚しました。
私と夫の間には、長男、長女がいますが、既に成人しています。
私は、夫と結婚後、子供が幼いときは、専業主婦として家事、育児に従事し、長女が幼稚園に入園してからは、パートとして勤務しています。
夫は、勤務先の会社を昨年退職し、現在、厚生年金を受給しています。
私は、まだ厚生年金の受給年齢に達していないため、年金は受給していません。
私は、夫と離婚することになりました。
私は、年金分割の制度があることを知りました。
私は、夫と離婚すると直ちに年金を受け取ることができるようになるのでしょうか。
結果
年金分割がされても、年金分割を請求した方が年金受給年齢に達しないと、年金は受給できないと考えられます。
6 離婚調停
離婚調停は、家庭裁判所における話し合いの手続です。当事者の方は、調停期日に出席して、調停委員を介して、相手方に意向などを伝え、相手方の意向などは、調停委員を介して伝わることが通常です。
離婚調停の手続において、離婚とともに年金分割の請求をすることができます。
離婚調停の手続において、当事者間で合意に達したときは、通常、調停調書を作成します。
離婚調停の手続において、離婚とともに、年金分割の合意をした場合には、調停調書をもとに、年金事務所において、年金分割の手続をします。
なお、家庭裁判所において、調停が成立した場合でも、法律が定めた期間内に、年金事務所に届出が必要になりますので、注意が必要です。
7 離婚訴訟
離婚訴訟において、付帯処分として、年金分割の請求をすることができます。
離婚訴訟では、当事者の方は、その主張を書面で提出したり、証拠を提出したりします。 離婚訴訟において、当事者間で合意に達した場合には、通常、和解調書を作成します。
離婚訴訟において、離婚とともに、年金分割を合意した和解が成立した場合には、和解調書をもとに、年金事務所において、年金分割の手続をします。
離婚訴訟において、和解が成立することなく、審理が終結し、判決において、離婚とともに年金分割が認められ、判決が確定したときには、判決書をもとに、年金事務所において、年金分割の手続をします。
家庭裁判所において、和解が成立した場合でも、判決が確定した場合でも、いずれの場合でも、法律が定めた期間内に年金分割の手続が必要になりますので、注意が必要です。
8 年金分割の審判
離婚が成立した後、年金分割について協議をしたものの合意に達しない場合、法律が定めた期間内であれば、家庭裁判所に年金分割の審判の申立をすることができます。
年金分割を認める審判が確定した場合、法律が定めた期間内に年金分割の手続が必要になりますので、注意が必要です。
9 年金分割請求の期限
年金分割請求については、基本的に離婚した日から2年以内に行う必要があります。
法律で定められた期限が徒過しないように、注意が必要です。
10 まとめ
個別の事案については、弁護士までご相談ください。
離婚、年金分割について、分からないことがありましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。
11 よくあるご質問
(1)年金分割と妻の年金
ご質問
私は、15年前に妻と結婚しました。
私と妻の間には、2人の子がいます。
私の妻は、結婚前から会社員として働いており、
産休、育休を取得しながら、現在も会社員として働いています。
私は、結婚前から現在に至るまで会社員として働いています。
私は、妻と不仲となり、妻は、子供を連れて実家に帰り、先月から別居しています。
妻は、私に離婚の申し入れをしてきました。
妻は、私に対し、離婚、子供の親権、養育費、財産分与の他に年金分割の主張をしています。
年金分割については、私の厚生年金だけが対象になるのでしょうか。
弁護士の回答
| 妻から年金分割の請求があった場合でも、夫の厚生年金だけでなく、妻の厚生年金も分割の対象となります。年金分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |  |
(2)年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
概要
私は、約25年前に夫と結婚しました。
私は、会社員として働いていましたが、出産を機に退職し、その後は、子供が幼稚園に入ってから、パートとして働き始めました。
私の夫は、ずっと会社員として働いています。
結婚後、私より夫のほうが、収入がずっと多く、また、私は、現在はパートなのですが、勤務時間が長いので、厚生年金に加入しています。
私は、昨年から夫と不仲になり、離婚を考えるようになりました。
私の夫は、離婚自体に応じる意思はあるのですが、年金分割には応じる意思はないようです。
私は、老後の生活を考えると、年金分割の手続きをしておきたいと考えています。私は、年金分割には、合意分割という制度と3号分割という制度があることを知りました。私は、婚姻期間中、厚生年金に入っていた期間があり、現在もパートですが、厚生年金に入っていますので、合意分割の手続きをしたいと考えています。
夫が年金分割に応じない場合、どうしたらよいのでしょうか。
なお、年金分割以外にも私と夫の意見が合わない箇所があり、協議離婚は難しいと思います。
結果

(3)年金分割は、再婚すると影響がありますか?
概要
私は、10年前に夫と結婚をしました。
夫は、結婚したときから、会社員として働いています。
私と夫の間には、長男、二男の二人の子がいます。
私は、夫と結婚した後、専業主婦でしたが、二男が保育園に行くようになってから、会社員として、働くようになり、厚生年金に加入していました。
私は、夫と不仲になり、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。
私は、昨年、夫と調停離婚し、長男、二男は私が親権者となり、養育費を支払ってもらうこととなり、年金分割をしました。慰謝料、財産分与は、互いに請求しませんでした。調停成立後、私は、年金事務所に行って、年金分割の手続をしました。
私は、その後、現在の夫と知り合い、結婚をすることになりました。
私は、再婚すると、すでに手続をした年金分割にも影響を与えるのでしょうか?
結果
一度なされた年金分割は、再婚をした場合でも、再婚を理由にさかのぼって影響を与えることはありません。
年金分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
(4)【Q&A】年金分割と届出の要否
概要
私は、15年前、夫と結婚をしました。夫は、結婚後、ずっと会社員として働いています。
昨年、夫が不倫をしていることが発覚し、私と夫は、不仲になりました。
私は、夫と離婚について話し合いをしたのですが、折り合いがつかず、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをするに至りました。
先日、離婚調停が成立し、私と夫は、調停において、年金分割の按分割合を0、5と定めることを合意しました。
私は、その後、家庭裁判所から調停調書を受け取りました。
私は、家庭裁判所で夫と年金分割の合意をし、調停調書を受け取ったので、年金分割についてこれ以上の手続きはしなくてよいでしょうか。
結果
| 家庭裁判所の調停で年金分割の合意をしただけでは、当然に年金分割されるものではありません。年金分割の届出等の法定の手続きが必要です。また、届出は、法定の期間内にする必要がありますので、注意が必要です。なお、当事務所では、ご依頼を受けた調停手続において、調停が成立し、年金分割が合意された場合、年金分割用の調停調書抄本をご依頼者の方に送り、速やかに届け出るようにお願いしています。年金分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |